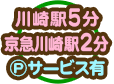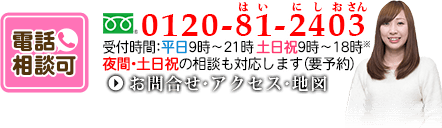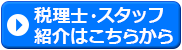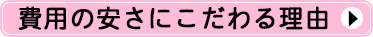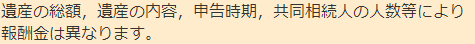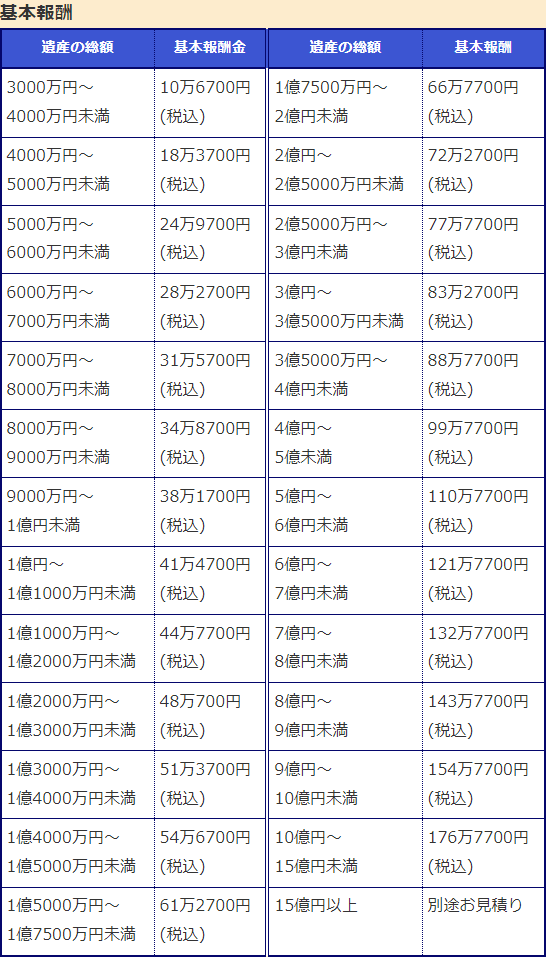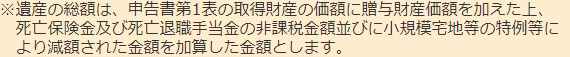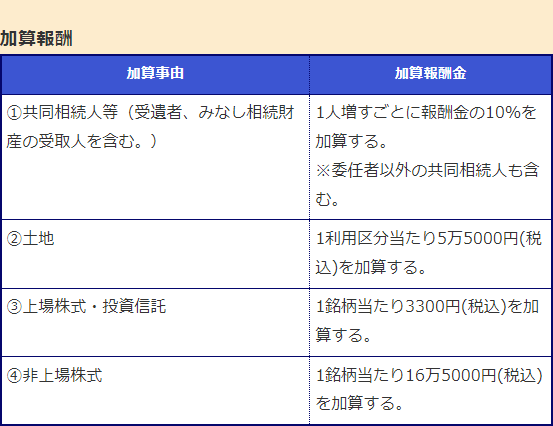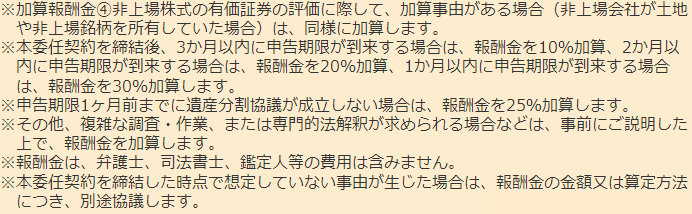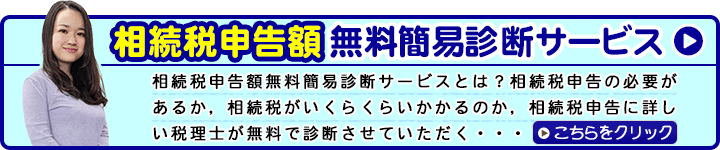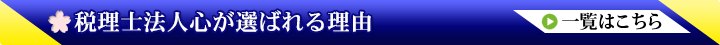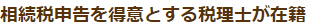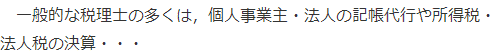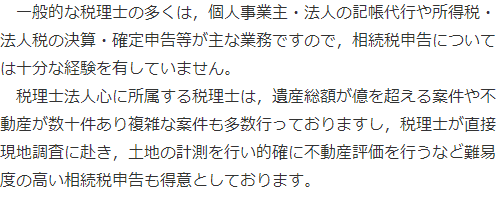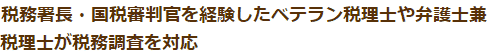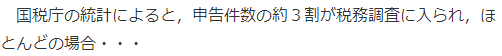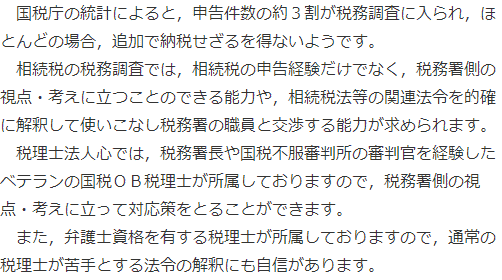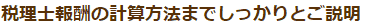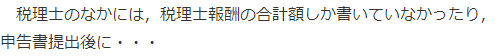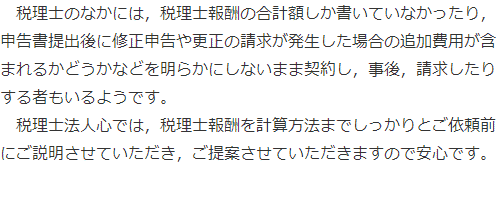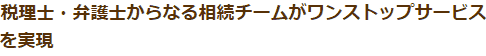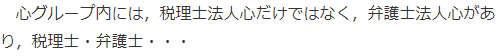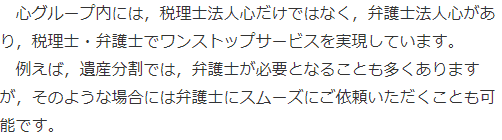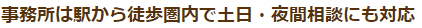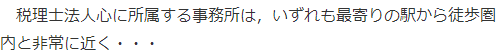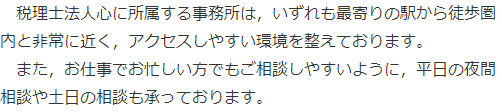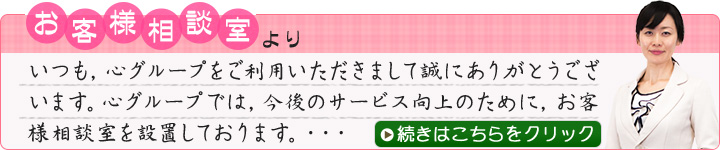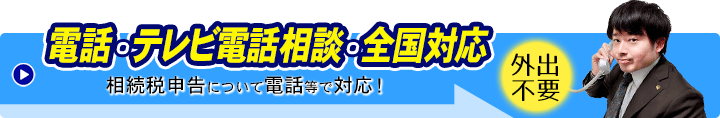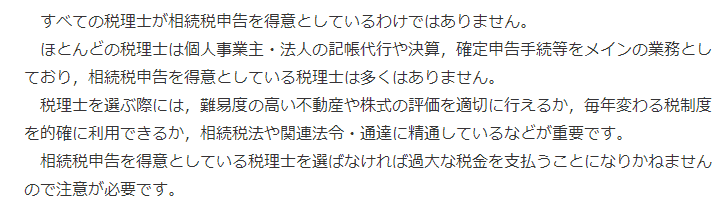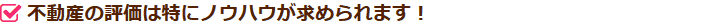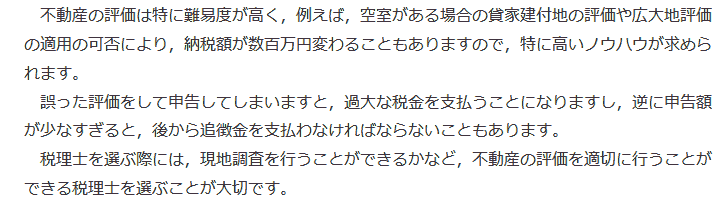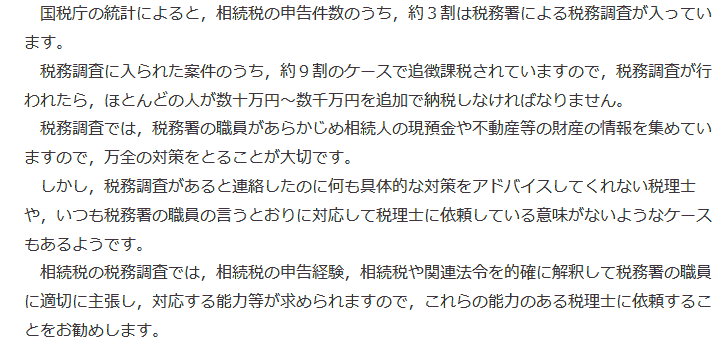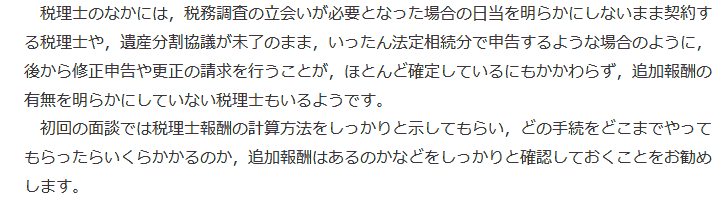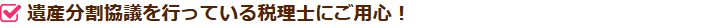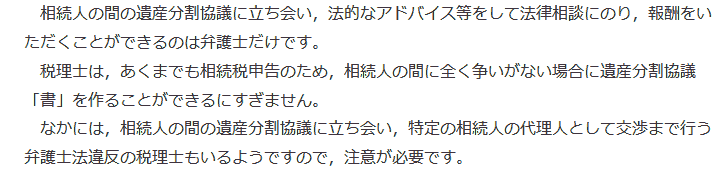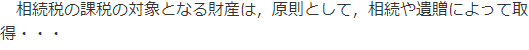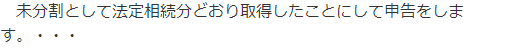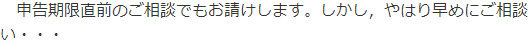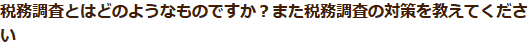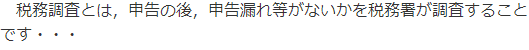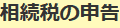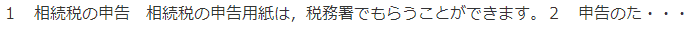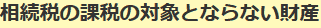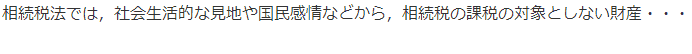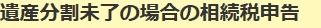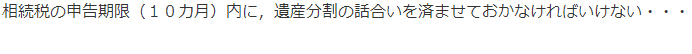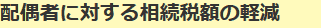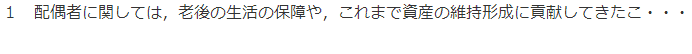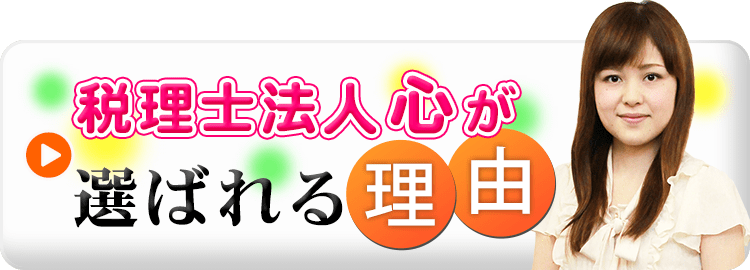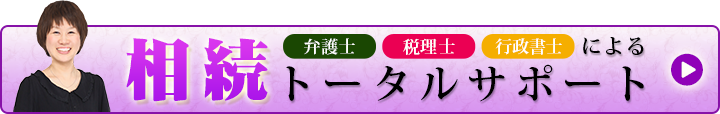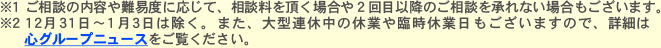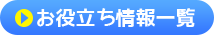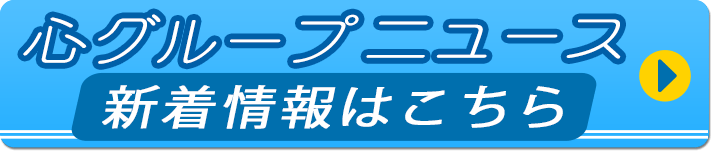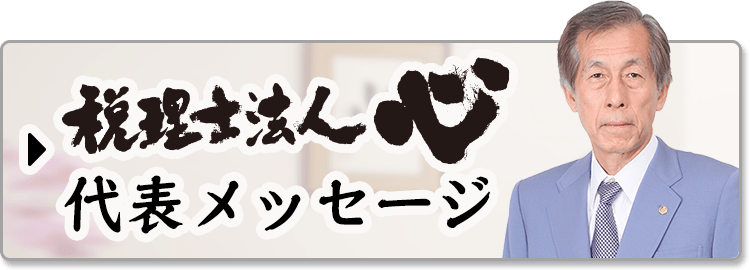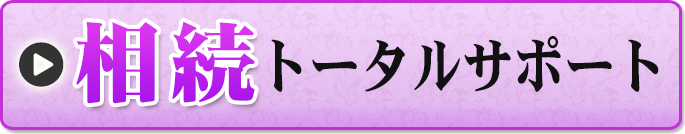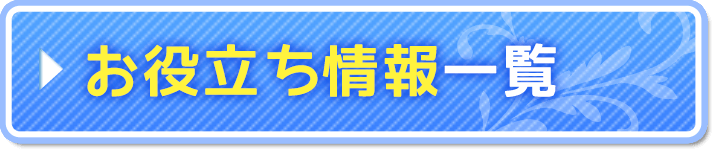相続税について税理士に相談すべきケース
1 遺産に不動産や非上場株式が含まれている場合

遺産の中に不動産や非上場株式が含まれている場合には、その評価をするのに専門的な知識が必要になります。
例えば、不動産の場合、遺産となる不動産の路線価価額や面積だけでは、適切に評価をすることができません。
不動産の間口や奥行の距離のほか、道路付けや不動産の字型によっても評価額が異なる可能性があります。
また、不動産の場合には、小規模宅地等の特例といった特例を使用できる可能性があります。
もっとも、その適用の可否を判断するのにも対象不動産の特性を踏まえて判断する必要があります。
そのため不動産の評価は、個別具体的に検討する必要がありますので、遺産に不動産が含まれる場合には税理士に相談する必要性が高いといえるでしょう。
非上場株式の評価についても個別具体的な判断が必要になります。
会社の規模や株主の構成によって評価方法が変わるうえ、会社の利益や配当金、純資産価額によって評価額は異なります。
そのため、自社株等の非上場株式が遺産に含まれる場合も税理士に相談した方が良いケースといえます。
2 近い将来に二次相続が発生する場合
近い将来に二次相続が生じるような場合、二次相続を見越して遺産の分け方を決める必要があります。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、一次相続では配偶者控除が使えますので、配偶者が全て遺産を取得したとしても1億6000万円までは相続税がかからないことになります。
一方で、被相続人の相続に次いで、当該配偶者の相続が発生した場合(二次相続)、当該配偶者の相続人は子供になります。
二次相続では配偶者控除が使用できませんので、子供が親(被相続人の配偶者)から相続した財産には、高額の相続税が課せられる場合もあります。
そのため、二次相続が見込まれる場合には、一次相続の段階で、一定の財産を子供に相続させておいて、二次相続に備えるということが必要になります。
二次相続を踏まえた相続税の試算には、専門的な知識が必要になりますので、税理士に相談した方が良いケースといえるでしょう。
3 過去に引出金や贈与がある場合
過去に引出金や贈与がある場合、当該引出金や贈与が相続税の課税対象財産に当たるかを確認する必要があります。
具体的には、預貯金等の取引明細書から過去の財産の移動の流れを確認して、相続税の課税対象となるかを検討することになります。
預貯金が複数ある場合、引出金や贈与が複数回ある場合には、確認の対象も多くなり、慣れないと確認に時間を要します。
そのため、このようなケースも税理士に相談することをおすすめします。